主体的学び研究所

41 リベラルアーツとは何かを問う(その1)
主体的学び研究所 顧問
土持ゲーリー法一
はじめに
「リベラルアーツ」ブームである。これは望ましい兆しであると考えたいが、同時に、「それだけでいいのだろうか?」という忸怩たる思いを感じるのは筆者だけだろうか。コロナ禍の影響で、これまで見過ごされてきたことに「メス」が入れられている。
巷では、「リベラルアーツプログラム for Business ~ビジネスに活きる新時代の教養を学ぶ」と題する動画が注目をされている。広告によれば、動画満足度「85%」以上だと言う。凄い数字である。裏を返せば、世の中のビジネス界がリベラルアーツの考えに「枯渇」している証である。
社会人になって初めて教養の必要性を感じる人が日本ではとても多く、その結果、今、教養ブームが起きているのだと思われる。
リベラルアーツが「動画」視聴だけで、本当に身につくのだろうか。甚だ疑問である。そうだとすれば、大学教育など必要ない。どこが問題なのか。それは、リベラルアーツを「知識」として捉える弊害から来ている。
リベラルアーツ教育というと、日本ではどういうプログラムを作るかという発想になるが、アメリカではそれは教育に対するアプローチのことである。つまり自分で考え、論理的な思考力や読解力、書く力など社会に出て役立つスキルを身に付ける学習方法であるから、当然、大学のカリキュラムで学ぶべきものである。
数年前、アクティブラーニングの導入が注目されたときと同じ誤りを繰り返している。その結果、未だに日本の学校にアクティブラーニングが浸透していない。これは、文科省の「責任」である。どこが間違っているか。それは、アクティブラーニングを知識として授けようとしているからである。本来、目指すべきは、アクティブラーニング「を」学ぶことではなく、アクティブラーニング「で」習得させるものでなければならない。
リベラルアーツにしろ、アクティブラーニングにしろ、「即効薬」はない。学校や大学の「カリキュラム」そして教員の教授法を通して自然に身につくものでなければ定着しない。すなわち、大学のカリキュラムや教員の教え方に左右される。
リベラルアーツの考えはアメリカに学べ
本コラムでは、上記のように問題意識から、アメリカにおけるリベラルアーツの事情を実際に体験的にまとめた、宮田敏近『アメリカのリベラルアーツ・カレッジ~伝統の小規模教養大学事情』(玉川大学出版部、1991年)を取りあげる。刊行年を考えると、アメリカのリベラルアーツ・カレッジの実態を紹介した先駆的な著書といえる。
「スワニー」という愛称で親しまれるサウス大学スワニーが描かれている。この大学は、創立以来150年にわたりリベラルアーツ教育に力を入れている大学である。
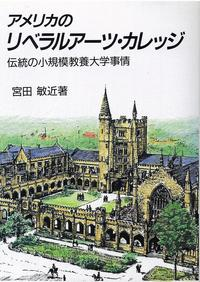
筆者は、「リベラルアーツとは何か」は安易に定義づけできないと考えている。なぜなら、そこには多様な考えが複雑に交差しているからである。これを「リベラルアーツプログラム」や「リベラルアーツ・カリキュラム」として一括りにしてしまうと、何か既存のものがあるかのように誤解されてしまう。それでは、リベラルな考えとは言い難い。リベラルアーツとは、人間の「生きざま」のようなものであると考えている。大学で教えられるのは、教員の断片的な考えに過ぎない。重要なことは、学生がどのように考えるかを引き出すところにある。
本著の「まえがき」で、「高等教育に関しては、アメリカは独自の伝統を確立している。中でも、『小規模教養大学』として知られるリベラルアーツ・カレッジは、もともと英国の伝統の流れをくむもので、若い国アメリカにあっても、特異な存在と言える。」(3頁)と述べ、その源流がイギリスの伝統に根ざすと述べている。そして、「1869年、ハーバードの学長に就任したチャールズ・エリオットは英米伝統型ともいうべき、保守的カリキュラムの特徴であった必修科目を大幅に減らし、学生の自由な選択にまかせた。」(17頁)と述べているように、アメリカの大学の特徴は、必修制を減らして、学生の自由な選択にまかせるという「単位制」の考えを示唆している。すなわち、リベラルアーツの源泉は、学生がリベラルな考えのもとで幅広く学ぶところにある。
また、英国とアメリカの大学の違いについても言及している。たとえば、「英国では大学教育を受ける前に、その能力があることを証明しなければならないが、アメリカではその能力がないと分かるまで、大学教育を受けられることだ」(27頁)と両者を興味深く峻別している。戦前日本の高等教育を考えれば、旧制高校がイギリスに近いものであったことが推察できる。
リベラルアーツ・カレッジは大学院を持たない
著者(宮田氏、以下同じ)は、「私立の小規模リベラルアーツ・カレッジの特色のひとつに、科学者や学者を多く育てることが指摘されている。そのような大学は多くの場合、田園地帯にあり、優れた教授でありつつもそこで教えることを選んだ者たちは、大学院がないためもあって、学部学生の教育に熱心である。」(48頁)と述べ、なぜ、リベラルアーツ・カレッジが優れた学士課程教育を提供しているかの理由の一端を紹介している。最近では、総合大学でもリベラルアーツ・カレッジを擁し、リベラルアーツ・カレッジでも大学院を有するところが見られる。
余談になるが、リベラルアーツ・カレッジの教員評価には、研究業績の有無はあまり影響がない。むしろ、教育業績が重視される。当然のことながら、学生による授業評価は、教員評価を決定づける要因となっていると言っても過言ではない。だからと言って、教員が学生に「迎合」することはない。学生による授業評価そのものは「無意味」である。なぜなら、教員評価の「一人歩き」になる危険性があるからである。教員が学生からの授業評価を省察してまとめた、ティーチングポートフォリオによってのみ評価されるところが重要である。
リベラルアーツ・カレッジと幅広い人間教育
著者は、専門だけに浸りこんでいるよりは、もっと幅広い人間教育が必要であると述べている。「専門教育に徹するオクスフォード、ケンブリッジによって代表される英国の大学は、いかに幅広い教育を施しているのか。」と問題提起し、それは、「何を教えるかより、いかに教えるかによる。偉大な真理を幅広く教えることよりも、『偉大なる方法』で教えることであるという。」(60頁)との同僚からの意見を紹介している。すなわち、「教授法」が違うというのがそうである。この「偉大なる方法」こそがリベラルアーツの真髄であると考える。換言すれば、いかに教えるかの「技法」にかかっている。そのためには、教員には幅広い教養が求められる。優れた大学は、教える内容だけでなく、いかに教えるかが「分岐点」となっている。
著者は、アメリカ南部の小規模リベラルアーツ・カレッジに滞在して、真正なカレッジのあり方を体験した。すなわち、「スワニーにおけるリベラルアーツ教育の真価は、その幅の広さもさることながら、それらの科目を『いかに教えるか』にあるといえる。」(61頁)と述べているところがそうである。これは重要な指摘である。リベラルアーツ科目という固有なものはない。どのような科目であっても教え方によってリベラルアーツ教育になり得る。それは、ひとえに教員の教授法にかかっている。したがって、特定の科目が適さないなどという理由はあり得ない。教員の工夫で克服できる。
これは日本の大学、とくに医学部と対比すると鮮明である。著者は「このようなリベラルアーツ・カレッジを出て医学大学院に入った学生は、専門化の傾向の強い他大学の卒業生に比べ不利ではないかとの問いに対し、むしろその逆であるという答えが返ってきた。(中略)それはリベラルアーツ・カレッジの卒業生は、基礎的なことを幅広くしっかりやっているからであり、また、人間としても他の人たちとのコミュニケーションにおいてすぐれており、将来医師となった際に大いに役立つはずである。それに加えて学生間の仲間意識、友情が強く、卒業後も長く続くと言う。」(78頁)とリベラルアーツ・カレッジの特徴を紹介している。
大学科目履修課程とは