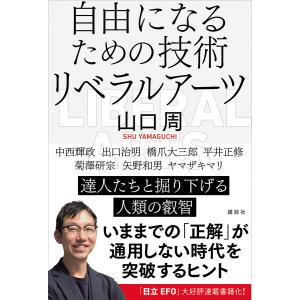39 リベラルアーツ教育は俯瞰的な学びに必要な技法(その1)
主体的学び研究所 顧問
土持ゲーリー法一
はじめに
なぜ、山口周氏の著書『自由になるための技術リベラルアーツ』(講談社、2021年)を取りあげるのか。それは、アートを「技術」と位置づけているからである。筆者(土持、以下同じ)もリベラルアーツを「固定概念」に囚われない、自由な考えを表現するアート(技法)だと考えていることと軌を一にする。
筆者は、リベラルアーツの考えを持つ人の一つの共通点に「社会性」があるのではないかと考えている。リベラルアーツを「教養」と捉えるときには、物事が「静止」した状態であって、社会とのつながりが見いだせない。動かなければ変わらない。著者も述べているように、古今東西の学者は「旅」をすることで知識のみならず、社会性も身に付けたのではないかと考える。
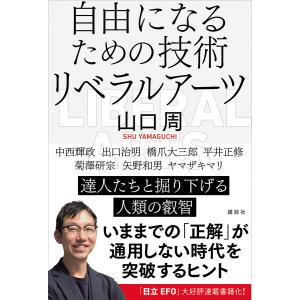
本書の特徴は、帯にも記載されるように、「達人たちと掘り下げる人類の叡智」と謳い、この分野の優れた識者から「ノウハウ(叡智)」をインタビューするという形態を取っている。著者(山口氏、以下同じ)のインタビューによるアプローチにも同感する。なぜなら、筆者も「オーラルヒストリー」にもとづいて、戦後教育史をドラマティックにまとめた経験があるからである。「ドラマティック」と述べたのは、インタビューは文書と違い、対談のなかで「ハプニング」があるからである。これを「副産物」と呼んでいる。人生には予期せぬ出来事が起こるもので、「人生の岐路」になることも経験則から学んだことがある。
著者は、リベラルアーツの技術を「達人たち」からの聞き取りとしているが、それは、著者にリベラルアーツ・マインドがあるからなせる技で、そうでなければ、単なる事実の「羅列」に過ぎない。本書を読み進めると、「質問」が頻繁に出てくる。理解を深めるために、「パラフレーズ」した表現が多々みられる。「脱線」とも取れるニュアンスも散見する。批判を恐れずに言えば、これはリベラルアーツに長けた人に共通するもので、話題が豊富で、話し上手で、比喩に富んで、「脱線」的なところもあるが、裏を返せば、社会性が豊かである証である。
本著についての「まえがき」はそのくらいにして、とくに、筆者が印象に残ったところを抜粋して2回に分けて紹介する。
リベラルアーツはなぜ必要なのか
著者は、現状を次のように分析している。すなわち、「アメリカの例のように、行き過ぎたサイエンスやエコノミーといった価値基準に対し、反対のベクトルへとバランスを取ろうとする動きは世界的な潮流にあると感じています。ハーバードやスタンフォードなど、アメリカの大学では、学部ではリベラルアーツ系の講義を中心に据えていることが多いのですが、2000年代の終わり頃からは、さらにそれを増やす方向へと大きく舵を切っているそうです。実学は大学院で学ぶものなのです。また、グローバル企業の多くが幹部候補生をMBA(経営学修士)ではなく美術系大学院へと送り込んでいること、アート系人材を次々と招聘していることなども、そんな最先端の潮流を物語っていると言えるでしょう。」(22頁)がそうである。
「論理的に考える力」が問われる時代に
著者は、出口治明氏との対談にこのような副題をつけている。出口氏は、「自ら学ぶ」ことについて取り上げ、「大学は何かを教える場所ではなく、自発的な学びを後押しする場所ですから、学生が自分のやりたいことを見つけられるよう、アクティブラーニングを積極的に取り入れています。ビュッフェのメニューのように多くのプログラムを用意して、その中から学生に好きなものをピックアップしてもらうという考え方で教育を行っています。」(84頁)と具体的な事例を示して説明している。
また、著者は歴史を振り返り、「日本の近代教育では、『西洋に追いつき追い越せ』という明治時代のモデルを継承し続け、自分で課題をつくる能力よりも、与えられた課題を速く正確に解く能力が求められてきました。しかし、それでは立ちゆかなくなってきたわけですね。」(85頁)と述べている。これは示唆に富んだ指摘であり、未だに発展途上国から「脱皮」できずに彷徨っている日本の姿が浮き彫りになっている。
「旅」についても言及している。出口氏は、「旅はいうまでもなく、五感で学べることに価値があります。情報というのは五感で入手するものですから、実際に現場に行くことで、映像で見るよりもはるかに多くの情報が得られます。あのデカルトも、大学の本を読み尽くした後、世の中の人々の考え方を知るべく旅に出たように、たくさんの人に会い、たくさん本を読み、たくさんいろいろな場所に行くこと以外に学ぶみちはありませんし、その学びは一生続くのです。」(98頁)と述べ、それを踏まえて、「一生学び続けるという意味では、リカレント教育の場としての大学の役割も、今後大きくなるのではないでしょうか。」との著者の問いかけに、出口氏は、「そうですね。大学の理想のあり方は、10世紀の終わりにカイロに創立された世界最古の大学の一つ、アズハル大学の教育信条に集約されていると思います。それが、『入学随時』『受講随時』『卒業随時』の三信条です。わからないことがあればいつでもおいで、自分の勉強したいことだけを学べばいい、そして疑問が解けたらいつでも卒業していい。その代わりまたわからないことが生じたら、いつでも学びにおいで。これこそが、リカレント教育をも含めた教育というものの真髄です。」(100頁)と説明している。これからもわかるように、リカレント教育の「起源」は、「自由」すなわちリベラルアーツであったことがわかる。
筆者は、「リカレント教育」について補足説明している。すなわち、「スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーンによって提唱された概念であり、義務教育や基礎教育の修了後に教育と教育以外の活動(仕事・余暇など)を交互に行う学習システム。1970年代にOECDで取り上げられ、国際的に知られるようになった生涯教育構想である。」(103~4頁)がそうである。これは1970年代のリカレント教育の「定義づけ」に過ぎず、それを現状に置き換えているところに現状の混乱がある。1970年以降、世界の教育は大幅に変わり、ITやAIという当時は想像もしなかった時代に直面している。やはり、新しいリカレント教育(ネオ・リカレント教育/Neo-Recurrent Education)のようなネーミングが望まれる。
対談では、「考える」に焦点が当てられ、「『考える』というと試験問題を解く力のように誤解されることがありますが、違いますね。」と出口氏に問いかけている。出口氏は「まったく違います。問いを立てる力であり、常識を疑う力です。」(108頁)と述べている。すなわち、「考える」ことそのことがリベラルアーツの原点ということになる。その事例として、「そのためには、例えば、デカルトが自らの常識を疑い、問いを立てるプロセスを書いた『方法序説』(フランス語)のような本を読み、追体験していくことで、ある種の型を覚えることが大事だということですね。」と著者が尋ねると出口氏は、「そうです。今後AI(人工知能)のような技術がさらに社会に浸透し、IT化が進むほど、リベラルアーツの力が大事になってくると思います。人間に問われているのは本質的に考える力なのですから。」(109頁)をあげている。
デカルトは、『方法序説』のなかで「我思う、故に我在り(Je pense, donc je suis.)」と述べ、「疑う」ことが真理を探究する原点であると主張している。仏教でも疑うことができるのは、「真理」を知っているからだと言われます。仏教に「五蘊仮和合(ごうんけわごう)ということばがある。五蘊とは色・受・想・行・識すべてのものは、この五蘊で成り立っている。すなわち、すべて仮の存在である。
考えるに関連して、「人間は考える葦である」というフレーズがある。これは、フランス哲学者・パスカルのことばである。葦とは水辺に育つ、弱く細い草のような植物のことで、パスカルは著書の中で、人間は自然の中では葦のように弱い存在である。しかし、人間は頭を使って考えることができる。「考える事」こそ人間に与えられた偉大な力である。
「考える人」の銅像を想起する者もいるかも知れない。これは、フランスの彫刻家・フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダン(以下、ロダン)の作品である。「考える人」は何を考えているのだろうか。誰しもが考えることである。実は、「考える人」は何も考えていないというのが真相のようである。「考える人」の元の作品、『地獄の門』は、ダンテの「神曲」から着想を得たもので、地獄に落ちた者たちを裁判官が上から見ている様子を表現しているといわれる。この裁判官が、「考える人」ということになる。BYUの渡部正和先生は、筆者との対談で「ロダンの考える人」は、「頭のてっぺんから足のつま先」までが「考える」ことを表現していて躍動感があると述べている。
著者の「『それは本当か』と疑うことができるかどうかは、幅広く物事を知っているかどうかに関わってくるわけですね。」との問いかけに、出口氏は「物事を正確に見るための方法論として、僕はよく『タテ・ヨコ・算数』と話しています。タテは歴史です。昔の人が物事についてどう考えていたかを知ることです。ヨコは他の国や違う業界です。日本社会の常識、業界の常識と思っていることが、世界ではどう見られ、考えられているのかを知ることも欠かせません。そして算数は、データやエビデンス、タテ・ヨコで学んだことを具体的な数字・ファクト・ロジックで把握するということです。」(110頁)と的を射た表現をしている。これは、「日本の常識は、世界の非常識」と言われるところにもつながる。算数は、数学のことであり、世界共通の客観的データを扱うことになる。アメリカの博士論文には、二つの高いレベルの外国語能力が求められるが、「統計学」を一つの外国語に代替する大学もあるほど重要視しているところもある。これは統計学が、研究上で必要不可欠との認識の表れである。
出口氏は、「『いろんな意見が出ると意思決定が遅くなるのでは』と反論する人がいます。ではグローバル企業はなぜ意思決定が速いのでしょうか。じつは、同質社会ほど忖度や空気を読むために意思決定が遅くなります。さまざまな意見や価値観の混在する異質な社会は、数字・ファクト・ロジックに基づいて考えるほかないために、かえって意思決定が速くなるのです。」(110~111頁)と逆に「反論」している。確かに、グローバル企業での意思決定が速いのは事実であるが、個々が自らの考えを主張でき、忖度しないからである。日本の話し方が相手に伝わりにくいのを改善するための3つのポイントがあると聞いたことがある。すなわち、①結論から話す、②短く話す、③数字で話す、がそうである。